Home » 武士道
祝い箸というものを考える
正月、新年明けましておめでとうございます。 新しいコロナとともにある時代。ないものねだりをしない。 それがくじけないコツだと思います。 しっかりと生きてゆきたいものです。 本年もよろしくお願いいたします。 さて、日本の正月の習慣には「祝い箸」というものが...
忍耐、我慢ということ
この表題のことは、あまりに最近しつこく言われていることだから改めて考えてみるべきだろう。 それは忍耐、我慢ということ。 目下のコロナ感染拡大の折、その自粛や対策への協力について、人々には「忍耐が強いられている」などと盛んに言われていることだ。 「人々は我慢に耐えかねてい...
享楽的なことは悪である
今は外国人との接点も多くなり、我が国にとって客人に過ぎなかった者が色々と口を出すようになった。 これさいわいと、これを利用して自らの堕落を糊塗しようとするのもいるし、日本文化を破壊しようと画策する者もいる。 なんということはない戦国時代が国境をまたいでいると考えれ...
食事を出されるときのこと
外食でもいい。客に呼ばれたとしてもいい。 我々はそうして、人に食事を出してもらうことがある。 出されたものに手をつける。 感謝し、礼節を持って応じる。 そこには時には薬味などがあって、それを自由に使えるようにされていることがある。 この時、出した女中や店主の目の前で薬...
「穏やかに過ごす」ということ
「穏やかに過ごす」と、人が言う。 よく隠棲した老人がそういう望みを口にしたりする。 しかし穏やかさとは呆けてしまうことではない。 そういう時、我々が大事にすべきこととは所作なのだと思う。 本を読んだり、手仕事をしたり、保存食の仕込をしたり、庭木の手入れをする。 それも...

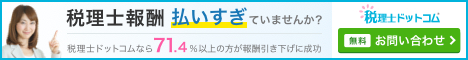


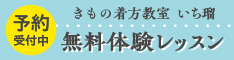



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a49101a.eeb23fdc.1a49101b.cd772170/?me_id=1275896&item_id=10000407&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchadougu%2Fcabinet%2F02999838%2Fimg58420346.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchadougu%2Fcabinet%2F02999838%2Fimg58420346.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
