Home » 食事
欧米のスープの飲み方から所作の決まりごとを考える
シチューを馳走になった。洋風の汁、スープ。 具の多いホワイトクリームシチューだ。 マッシュルーム、豚肉、海老、人参、ジャガイモ、インゲン、そしてキャベツ。 市販のクリームシチューのルーをベースに生クリームを追加して作ったもの。 炒めたタマネギとマッシュルーム、そこに...
祝い箸というものを考える
正月、新年明けましておめでとうございます。 新しいコロナとともにある時代。ないものねだりをしない。 それがくじけないコツだと思います。 しっかりと生きてゆきたいものです。 本年もよろしくお願いいたします。 さて、日本の正月の習慣には「祝い箸」というものが...

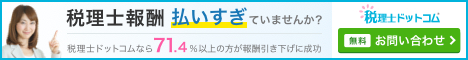
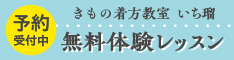



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a49101a.eeb23fdc.1a49101b.cd772170/?me_id=1275896&item_id=10000407&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchadougu%2Fcabinet%2F02999838%2Fimg58420346.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchadougu%2Fcabinet%2F02999838%2Fimg58420346.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
